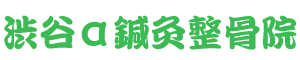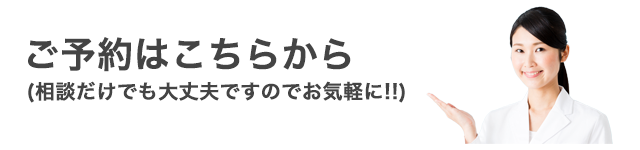パーキンソン病とは
パーキンソン病は、主に中高年以降に発症する神経変性疾患の一つで、運動機能に関わる症状を引き起こします。この病気は、脳の一部である「黒質」という部分にある神経細胞が徐々に失われることで起こります。黒質は、ドーパミンと呼ばれる神経伝達物質を生成する役割を担っています。ドーパミンは、体の動きを調整するために非常に重要な物質です。ドーパミンの不足により、手足の震え(振戦)、筋肉のこわばり(筋強剛)、動作の遅れ(寡動)、姿勢やバランスの障害といった特徴的な症状が現れます。

パーキンソン病の症状
パーキンソン病の症状は徐々に進行し、初期は軽微なものですが、次第に日常生活に大きな支障をきたすようになります。以下は、主な症状の説明です。
1. 振戦(しんせん)
振戦とは、手や足、顔などが無意識に震える症状です。特に、安静にしているときに手が震えることが多く、これを「安静時振戦」と呼びます。パーキンソン病患者の多くは、最初にこの安静時振戦を経験し、その後他の運動症状が現れます。
2. 筋強剛(きんきょうごう)
筋肉のこわばり、つまり筋強剛は、身体の動きが硬くなる状態を指します。パーキンソン病では、関節の動きがスムーズでなくなり、身体全体に緊張が生じます。この筋肉の硬直が原因で、動作がぎこちなくなることがあり、姿勢が不自然になることもあります。
3. 寡動(かどう)・無動
寡動とは、動作が遅くなることを指し、無動は、動きそのものが困難になる状態を指します。日常的な動作、例えば歩く、服を着る、文字を書くといった活動が徐々に困難になります。また、表情が乏しくなる「仮面様顔貌」と呼ばれる症状が現れ、話し方が単調になることもあります。
4. 姿勢保持障害
パーキンソン病が進行すると、姿勢やバランスを保つことが難しくなります。転びやすくなる、体が前傾して歩く、足がうまく動かなくなる「すくみ足」といった症状が現れます。これにより、歩行が不安定となり、日常生活で転倒のリスクが高まります。

非運動症状
パーキンソン病は、運動に関連する症状だけでなく、非運動症状と呼ばれるさまざまな身体的・精神的な症状も引き起こします。これらの非運動症状も患者の日常生活に大きな影響を与えるため、適切な対策が必要です。
1. 自律神経症状
自律神経の働きが乱れることで、便秘、排尿障害、血圧の変動、発汗異常などが現れます。特に便秘は、パーキンソン病患者に非常に多く見られる症状の一つです。また、立ち上がった際に急激に血圧が下がる「起立性低血圧」もよく見られます。
2. 睡眠障害
パーキンソン病患者の多くは、睡眠障害を経験します。不眠症、夜間に何度も目が覚める、レム睡眠行動障害(夢の中で体が実際に動く症状)などが一般的です。
3. 抑うつ・不安
パーキンソン病は、脳内のドーパミン不足だけでなく、セロトニンやノルアドレナリンといった他の神経伝達物質にも影響を与えるため、抑うつや不安感が現れることがあります。これにより、気分の落ち込みや無気力感が増すことがあります。
4. 認知機能の低下
病気が進行すると、記憶力や集中力の低下、判断力の鈍りなど、認知機能に影響が及ぶことがあります。一部の患者では、パーキンソン病に関連した認知症を発症することもあります。

パーキンソン病の原因
パーキンソン病の明確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関連していると考えられています。
1. 加齢
加齢はパーキンソン病の最大のリスク要因です。年齢を重ねることで、脳内の神経細胞が自然に減少し、ドーパミンの産生が低下することが原因の一つとされています。特に60歳以上の高齢者に発症しやすい傾向があります。
2. 遺伝的要因
パーキンソン病の大部分は遺伝とは関係がないとされていますが、家族にパーキンソン病の患者がいる場合、発症リスクがやや高まることが分かっています。特定の遺伝子変異が関連していることもあり、これにより発症する家族性のパーキンソン病も存在します。
3. 環境要因
農薬や化学物質への長期間の曝露がパーキンソン病のリスクを高める可能性があるとされています。また、頭部外傷なども、リスクを増加させる要因の一つと考えられています。
パーキンソン病の西洋医学的な対策
1. 薬物療法
パーキンソン病の主な治療法は、ドーパミンを補う薬や、ドーパミンの働きを補助する薬物療法です。最も一般的に使用される薬は「レボドパ」で、これを服用することで体内でドーパミンに変わり、運動症状を緩和します。また、ドーパミン受容体刺激薬や、モノアミン酸化酵素阻害薬(MAO阻害薬)なども使用されます。
2. リハビリテーション
リハビリテーションは、筋力やバランスの維持、歩行機能の改善に役立ちます。運動療法や理学療法を通じて、患者ができる限り自立した生活を送れるように支援します。
3. 外科的治療(脳深部刺激療法:DBS)
重症化した場合には、脳の深部に電極を埋め込んで電気刺激を与える「脳深部刺激療法(DBS)」という手術が行われることがあります。これにより、運動症状を軽減する効果が期待されます。
パーキンソン病の東洋医学
パーキンソン病に対する東洋医学や鍼灸治療は、病気の進行を遅らせたり、症状を緩和したりするための補完的なアプローチとして注目されています。東洋医学では、パーキンソン病を「痿証(いしょう)」や「振顫(しんせん)」などの概念に関連付けて理解し、体全体のバランスを整えることを重視します。鍼灸治療では、気血(きけつ)の流れを整え、症状の緩和や体力の回復を目指します。
東洋医学では、パーキンソン病のような運動障害や震えを伴う病気は、主に「気」「血」「陰陽」の不調や「肝」「腎」といった臓腑の機能低下と関係があると考えます。これらのバランスが崩れることで、体内のエネルギーの流れが滞り、神経系統に影響を与えるとされます。
1. 肝の不調
東洋医学では、「肝」は身体の動きを円滑にする役割を持ち、筋肉や腱を司っています。肝の機能が低下すると、気の巡りが滞り、筋肉のこわばりや震え、スムーズな動作ができなくなる「肝風内動」と呼ばれる状態が生じます。これが、パーキンソン病の運動障害に関連すると考えられます。
2. 腎の虚弱
「腎」は生命エネルギーの貯蔵庫とされ、身体全体の成長、発育、老化を司るとされています。パーキンソン病は加齢とともに発症することが多く、「腎虚(じんきょ)」と呼ばれるエネルギー不足の状態が関与していると考えられます。腎が弱ると、体の精気が不足し、筋力や運動機能が低下しやすくなります。
3. 気血の不足
東洋医学では、「気」と「血」が身体を循環し、健康を保つと考えられます。パーキンソン病では、この気血が不足したり滞ったりすることで、運動障害や疲労感、震えが引き起こされると考えられています。特に、年齢とともに気血が不足しがちになるため、パーキンソン病の症状が進行する一因とされています。
4. 陰陽のバランスの乱れ
「陰陽」のバランスが崩れると、身体の機能が正常に働かなくなります。特に、パーキンソン病では、陰の不足(陰虚)によって体内の熱が過剰になり、それが震えやこわばりを引き起こすとされています。

パーキンソン病の鍼灸治療
鍼灸治療は、気血の流れを調整し、臓腑のバランスを整えることで、パーキンソン病の症状を緩和することを目指します。具体的には、特定のツボ(経穴)を刺激することで、運動機能の改善や症状の軽減を図ります。
1. 気血を巡らせ、肝腎を強化するツボ
・足三里(あしさんり): 脚に位置し、消化器系や気血の巡りを改善するためのツボです。体力の回復や疲労軽減に効果があり、パーキンソン病患者のエネルギー不足を補います。
・太渓(たいけい): 足首の内側に位置し、腎の機能を強化するツボです。腎虚による筋力の低下や疲労を改善し、体全体のバランスを整えます。
・肝兪(かんゆ): 背中にあるツボで、肝の機能を調整し、筋肉の緊張を緩和します。肝風内動の抑制にも効果的とされています。
2. 震えや筋肉のこわばりを緩和するツボ
・百会(ひゃくえ): 頭のてっぺんにあるツボで、全身の気の巡りを改善し、精神的な安定にも効果があります。手足の震えを抑えるために使用されます。
・合谷(ごうこく): 手の甲にあるツボで、全身の気の流れを調整し、筋肉のこわばりや緊張を緩和します。特に震えや緊張に効果的です。
・太衝(たいしょう): 足の親指と人差し指の間にあるツボで、肝のエネルギーを調整し、筋肉のこわばりを和らげる効果があります。運動障害の緩和にも有効です。
3. 精神的な不安や抑うつの緩和
・内関(ないかん): 前腕に位置し、心の安定を促すツボです。パーキンソン病の非運動症状である不安や抑うつを軽減し、ストレスの緩和にも役立ちます。
・神門(しんもん): 手首にあるツボで、心の安定を図るために使用されます。リラックス効果があり、精神的な緊張をほぐすのに役立ちます。
4. 腎虚を補い、全身のバランスを整えるツボ
・三陰交(さんいんこう): 脚の内側にあるツボで、気血を補うだけでなく、腎や脾の機能を強化します。全身のエネルギーを補い、筋力の低下や疲労感を改善します。
・関元(かんげん): お腹の下部に位置し、腎の機能を強化するツボです。体力を補充し、気血の不足を改善します。

まとめ
鍼灸治療は、西洋医学の薬物療法やリハビリテーションと併用されることが多く、総合的な治療として用いられます。鍼灸治療は次のような効果が期待されています。
・運動症状の緩和: 鍼灸治療は、筋肉のこわばりや震えを和らげ、運動能力の改善に役立つことが報告されています。また、歩行や動作のスムーズさが向上し、日常生活の質を高める効果が期待されます。
・非運動症状の軽減: 睡眠障害や便秘、抑うつなど、パーキンソン病の非運動症状にも鍼灸が有効とされています。自律神経系への働きかけによって、これらの症状の緩和が図られます。
・精神的な安定: 鍼灸治療は、リラックス効果があり、ストレスや不安を軽減するため、精神的な安定を促進します。これにより、パーキンソン病患者がより穏やかな気持ちで過ごすことができるようになります。
パーキンソン病に対する東洋医学と鍼灸治療は、症状を緩和し、生活の質を向上させるための補完的なアプローチとして有効です。鍼灸は、気血の流れを整え、臓腑の機能を高めることで、運動障害や非運動症状の改善を目指します。
また、患者一人ひとりの体質や症状に合わせた個別の治療が行われるため、西洋医学の治療と並行して取り入れることで、より良い結果が期待できます。