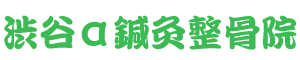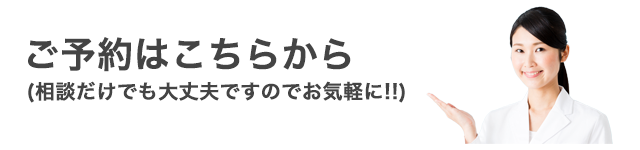パニック障害とは
パニック障害は、突然強い不安や恐怖におそわれ、動悸やめまい、息苦しさといった体の症状を伴う心の病気です。発作が起きても心臓や肺に異常があるわけではなく、自律神経が一時的に過剰に反応しているだけなので命にかかわることはありません。ただし、発作を繰り返すうちに「また起きるのでは」という不安(予期不安)が強くなり、人前に出ることが怖くなったり、一人で外出できなくなったりする「広場恐怖症」に進むことがあります。
パニック障害の原因
この病気の背景には脳の働きのアンバランスや強いストレス、もともとの体質などが関係しています。私たちの脳には危険を察知して心臓の鼓動を早めたり、血圧を上げたりして体を守ろうとする仕組みがあります。その中心となるのが扁桃体という部分で、不安や恐怖に深くかかわっています。通常はセロトニンという神経伝達物質が働いて気持ちを落ち着けていますが、パニック障害ではこのセロトニンが不足しているため、不安の信号が過剰になってしまうと考えられます。そこに長引くストレスや、もともと不安を感じやすい体質が重なると発症のリスクが高まります。
治療について
治療は「薬」と「心のケア」の両方から行います。薬によって脳のバランスを整え、発作をコントロールします。一方で、不安を感じたときの考え方や心のクセにアプローチするためには、認知行動療法や心理教育といった精神療法が役立ちます。薬だけでは不安の連鎖を断ち切ることが難しいため、心と体の両面でケアをすることが大切です。
鍼灸によるサポート

鍼灸もパニック障害の改善に役立つとされています。鍼やお灸で自律神経のバランスを整え、過剰に働いている交感神経を静めてリラックスを促します。また、血流を良くして体の緊張をほぐすことで、めまいや動悸といった症状の緩和が期待されます。さらに、鍼灸にはセロトニンの分泌を助ける作用があると考えられており、気持ちを落ち着けやすくする効果も報告されています。
発作が起きたときの工夫
実際に発作が起きたときは、まず「命にかかわることはない」と自分に言い聞かせましょう。次のような工夫で落ち着きやすくなります。
前かがみになり、自然にお腹で呼吸できる姿勢をとる
息を「吸う:吐く=1:2」の割合にして、10秒ほどかけてゆっくり吐く
手首にある「神門」というツボを押しながら「すぐ落ち着く」と唱える
これらは呼吸を整え、不安をやわらげるのに役立ちます。
まとめ
パニック障害は突然襲ってくる強い不安が特徴ですが、命に関わるものではなく、正しい治療や工夫で改善していける病気です。薬や心理療法に加えて、鍼灸なども取り入れながら、自分に合った方法で心と体を整えていくことが大切です。そして「そのうち必ず落ち着く」と考え、発作に必要以上に恐怖を抱かないことが回復への一歩になります。