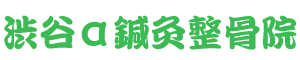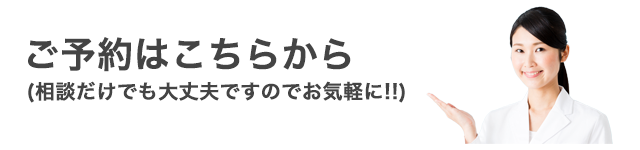原因
声帯炎とは、声をつくるために重要な「声帯」に炎症が起き、声がかすれたり、出にくくなったりする病気です。主な原因はウイルスや細菌感染によるもので、風邪の一症状として現れることが多く、タバコやお酒、乾燥した空気、職業的な声の酷使なども誘因となります。炎症によって声帯粘膜が腫れ、発声時にきちんと閉じなくなるため、声がガラガラしたり、ささやき声しか出せないといった状態になります。
治療
一般的な治療は、炎症の原因や重症度に応じて対症療法を行います。痰を取り除く去痰薬、炎症を鎮める薬、細菌の関与が疑われる場合には抗生剤が用いられることもあります。喉を使いすぎたことが原因の場合、ステロイドの投与で炎症の腫れを早く改善させる方法もありますが、その副作用としてむくみや不眠、情緒の変動が出る場合があります。いずれの場合も最も大切なのは「声の安静」です。炎症が残るうちに無理な発声を続けると、声帯結節やポリープといった慢性的な障害に発展し、治療が長引くことがあります。
声の枯れを起こす病気
声のかすれや声枯れを起こす病気は、声帯炎以外にも、声帯の摩擦による結節や出血によるポリープ、甲状腺機能の低下、胃酸逆流による炎症、さらには咽頭がんの初期症状として現れる場合もあります。長期間にわたり声の異常が続く場合は、必ず専門医の診断を受けることが重要です。
東洋医学的視点
東洋医学では、声帯炎や声枯れを「肺の機能低下」と関連づけて考えます。肺は東洋医学で呼吸と声を司る臓とされ、外界からの邪気に対する防御力=免疫力とも深く関わります。肺の働きが弱まると、喉の乾燥や炎症を起こしやすくなるため、治療では肺の機能を整えることを重視します。同時に、慢性的な声の不調や疲労が続く人の中には「腎」の働きが低下している方も多く、これは生命力や回復力の不足を示します。したがって、鍼灸では肺と腎のバランスを整えるような経穴(ツボ)を選んで施術を行います。

鍼灸治療には、血流を促進し炎症を鎮める作用、喉や頸部の筋肉の緊張をやわらげる作用、自律神経のバランスを整える作用があります。具体的には、喉の炎症を抑えるために天突(てんとつ)や廉泉(れんせん)などの局所のツボ、免疫調整目的で合谷(ごうこく)や足三里(あしさんり)など全身に影響するツボを用います。お灸によって局所の血流を高め、冷えた喉を温めることで、自然治癒力を引き出します。
自律神経系の関与
また、現代の生活ではストレスや過労によって自律神経のバランスが崩れ、これが声の不調につながるケースも増えています。声帯を支配する喉頭筋群は迷走神経を介して副交感神経と深く関係しており、緊張状態が続くと声がかすれたり息が詰まりやすくなります。当院では自律神経を客観的に測定し、交感神経と副交感神経のバランスを確認した上で施術を行います。自律神経を整えることで、喉の過緊張を解き、発声しやすいリラックスした状態をつくることができます。

さらに、睡眠の質を改善することも鍼灸治療の大きな目的の一つです。質の高い睡眠は成長ホルモンの分泌を促し、傷んだ声帯や疲れた筋肉の回復を助けます。ストレスを受けやすい現代人にとって、心身の両面から回復を支援する鍼灸療法は、声帯炎の再発防止にも有効です。
東洋医学では、体の不調を単なる局所の問題とは捉えず、全身のバランスの乱れとして理解します。喉の炎症は肺や腎だけでなく、気血の巡りの滞り、ストレスによる気の上衝(気が頭に上る状態)として現れることもあります。これらを総合的に整えることで、炎症の鎮静、免疫力の向上、精神的な安定を同時に図ることができます。
まとめ
声枯れが長引く、無理をするとすぐ声が出なくなる、そんな方は単に喉だけでなく、体全体の調子を整える視点が必要です。鍼灸治療は、声帯炎という局所症状だけでなく、体の内側から声を支え直す方法です。声を使う仕事の方、繰り返す声枯れに悩む方は当院にご相談ください。