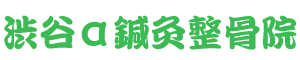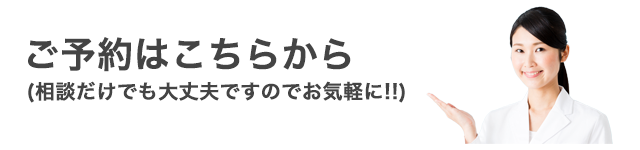耳管開放症とは
耳管開放症(じかんかいほうしょう)は、耳と喉の間にある「耳管(じかん)」という通り道が常に開いた状態になる病気です。通常、耳管は飲み込んだり、あくびをしたりするときに一時的に開き、耳と喉の間の気圧を調整する役割を果たしています。しかし、耳管開放症では、この耳管が日常的に開きっぱなしになってしまい、耳に違和感を覚えたり、自分の声が響くように感じたりします。症状は一見軽いように見えるかもしれませんが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
耳管の役割
耳管は、耳の鼓膜の内側にある中耳と喉の奥の部分(鼻の奥にある咽頭)をつなぐ細い管です。通常、この管は閉じていますが、気圧の差を調整するために一時的に開きます。飛行機に乗ったときや山道を登ったときに、耳が「詰まる」感覚を覚えることがありますが、耳管が正常に機能していれば、あくびをしたり、唾を飲み込んだりすることでこの詰まりが解消されます。
耳管が適切に開閉することで、中耳の気圧が外の気圧と等しくなり、鼓膜が正常に振動して音が聞こえるようになります。しかし、耳管が開きっぱなしの状態になると、中耳と鼻の奥が直接つながってしまい、耳にさまざまな不快な症状が現れます。
耳管開放症の症状
【自声強聴】(じせいきょうちょう)
自分の声が耳の中で響く感覚です。普通は外の世界で聞こえる音が耳に入りますが、耳管開放症の方は自分の声がこもったように大きく感じられ、話すのが不快になります。これにより、会話がしづらくなり、特に静かな場所ではストレスを感じることがあります。
【耳の閉塞感】
耳が詰まったような感覚を持つことがあります。耳を塞がれている感じがするため、音がくぐもって聞こえたり、外部の音を遮断してしまうように感じたりすることがあります。
【呼吸音の聞こえ方】
呼吸をするたびに自分の呼吸音が耳の中で響くこともあります。これは耳管が開いた状態で、空気の流れが耳の中に伝わるために起こります。
【めまいやふらつき】
耳の問題から、平衡感覚に影響を及ぼすことがあり、めまいやふらつきを感じることがあります。
耳管開放症の原因
耳管開放症の原因ははっきりとは分かっていませんが、いくつかの要因が関係しているとされています。代表的なものには以下のような要因があります:
【体重減少】
急激な体重減少が耳管開放症の引き金になることがあります。耳管の周りには脂肪組織があり、これが耳管の閉鎖をサポートしています。体重が減少するとこの脂肪組織も減少し、耳管がうまく閉じなくなることがあります。
【妊娠】
妊娠中はホルモンバランスの変化や体のむくみによって、耳管の機能が一時的に乱れることがあります。
【加齢】
年齢を重ねるにつれて、耳管の筋肉や周りの組織が弱くなることがあります。そのため、耳管が閉じにくくなり、開きっぱなしの状態が生じることがあります。
【ストレスや疲労】
精神的なストレスや極度の疲労が耳管の開放に関連することが報告されています。これらの状態が体の他の部分に影響を与えるように、耳の機能にも影響を与えることがあります。
西洋医学的な対策
ストレスによる自律神経・ホルモンバランスの乱れから起こるケースが多く、明確な原因がないため下記のような対策が必要になります。
・生活習慣の見直し
・点鼻薬の使用
・耳管プラグ挿入術

耳管開放症の東洋医学
東洋医学では、体内の「気」と「血」の循環が重要な役割を果たしているとされ、これが正常に流れることで健康が保たれると考えます。耳管開放症は、東洋医学の観点から以下のような要因が関連しているとされています。
【気虚(ききょ)】
「気」の不足によって体の機能が弱まり、耳管が正常に閉じられなくなることがあります。気虚の症状には、疲れやすさ、息切れ、声のかすれなどが含まれ、体全体のエネルギー不足が原因で耳管の筋肉や周囲の組織が弱まることがあると考えられます。
【血虚(けっきょ)】
「血」が不足し、体の栄養や潤いが不足することも原因の一つとされています。血虚によって耳周辺の筋肉や組織が十分に栄養されず、耳管がうまく機能しなくなる可能性があります。
【湿熱(しつねつ)】
体内の「湿気」や「熱」が滞っている状態で、これが耳管周囲の組織や筋肉に影響を与えることがあります。湿熱は、体の内部に過剰な湿気や熱がこもり、これが耳管の開閉機能を阻害すると考えられています。湿熱の原因としては、飲食の不摂生や過労などが挙げられます。
耳管開放症に対する鍼灸治療
当院では、全身の自律神経に対する施術と耳の局所施術の2つが大まかな施術です。
全身の鍼灸では手や足のツボ(合谷や太谿など)を使って施術していきます。
次に耳周囲に鍼を行い、耳の血流を促進させます。
首肩周りの筋肉に硬さがあると血流の滞りにつながるため、首肩の筋肉への施術も行います。
【主なツボ】
・翳風(えいふう):耳の後ろに位置し、耳の不調を改善するための代表的なツボです。
・太谿(たいけい):足首の内側にあり、腎経に属するツボで、体全体の気を補う効果があります。
・合谷(ごうこく):手の甲の親指と人差し指の間にあるツボで、気の流れを促進し、全身の調整を図ります。